この記事は7分で読めます
正社員が会社を辞める理由第1位は
「人間関係の悩み」だと知っていますか?
上司との相性・職場の雰囲気・パワハラなど、実は多くの退職理由が、職場のストレスに関係しています。
そうした背景もあり、2015年12月からは『ストレスチェック制度』が導入され、従業員50人以上の事業場では実施が義務化されました。
しかし、50人未満の中小企業には法的義務はありません。それでもいま、ストレスチェックを取り入れる企業が増えています。
その理由の一つが、「健康経営優良法人認定制度」。
ストレスチェックの実施が評価の対象となり、認定を受けるうえで必要な取り組みです。

Sailing Dayの羊一です。
今回は、中小企業がストレスチェックを導入するメリットや実施方法、健康経営優良法人との関係性などを分かりやすく解説します。
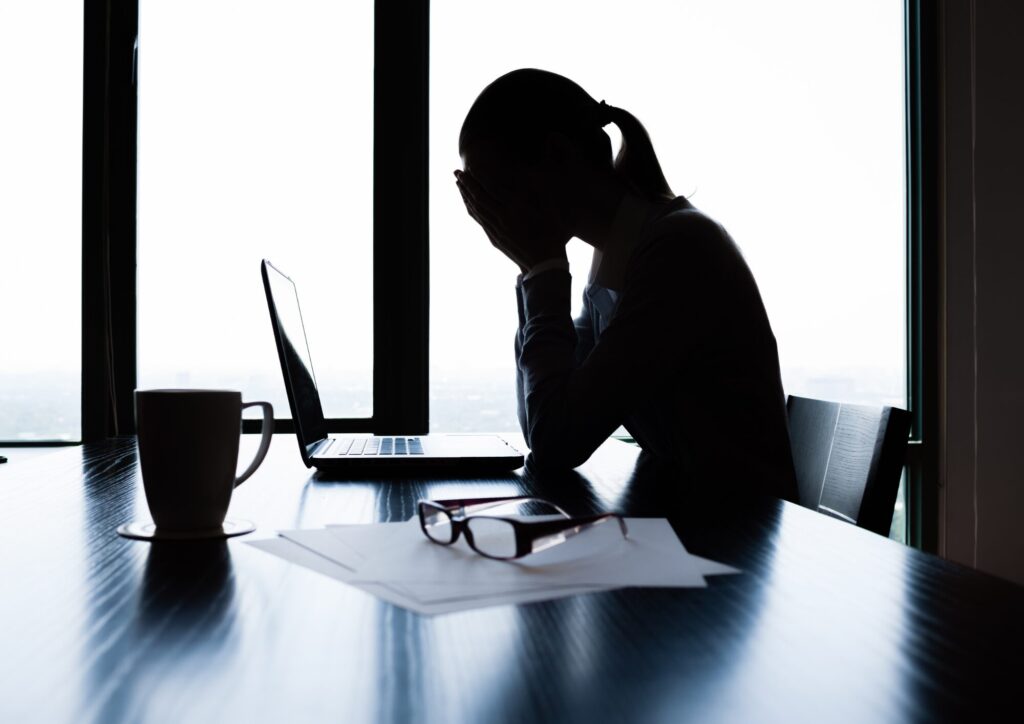
1.ストレスチェックを導入するメリット
ストレスチェックは、単なる“アンケート”ではありません。
従業員と会社、どちらにとっても「早めに気づける仕組み」として、大きな役割を果たします。
(1)そもそもストレスチェックとは?
「ストレスチェック」 とは、 ストレスに関する質問票 (選択回答)に労働者が記入し、それを集計・分析することで、自分のストレスがどのような状態にあるのかを調べる簡単な検査です。
「労働安全衛生法」という法律が改正されて、常時、労働者が50人以上いる事業場では、2015年12月から、毎年1回、この検査を全ての労働者※に対して実施することが義務付けられました。
※ 契約期間が1年未満の労働者や、労働時間が通常の労働者の所定労働時間の4分の3未満の短時間労働者は義務の対象外です。

つまり、従業員のストレスの原因や強さを“見える化”することです。
まず「常時、労働者が50人以上いる事業場」の定義について解説します。
「常時、労働者が50人以上いる事業場」の常時とは?
期間の定めのない雇用契約、または1年以上継続して雇用される見込みがあり、週の所定労働時間が通常の労働者のおおむね4分の3以上である労働者を指します。
(厚生労働省「ストレスチェック制度実施マニュアル」より)

つまり、正社員に限らず継続的に勤務しているパート・アルバイト・派遣社員なども含まれます!
「常時、労働者が50人以上いる事業場」の事業場とは?
企業の本社・支店・営業所・工場・店舗など、所在地ごとに区分された単位を指し、同一法人であっても場所が異なれば別の事業場として扱われます。

つまり、複数拠点をもつ企業ではそれぞれの事業場ごとに「常時使用する労働者数」が50人以上かどうかを判断する必要があります。
(2)ストレスチェック実施のメリット
【労働者側】
◎自分のストレス状態に気づける
日々忙しく働く中で、自分がどれだけストレスを感じているかを見落としがち。
◎早めに気づいて悪化を防げる
「なんかしんどいな…」という曖昧な不調も、ストレスチェックで“見える化”すれば、早めに相談や対策が可能になります。
◎相談しやすい環境が整う
会社がストレスチェックを行うことで、「心の健康もちゃんと見てくれているんだ」と安心感が生まれ、悩みを話しやすい雰囲気につながります。
◎職場環境が良くなるチャンス
集団での結果をもとに、働きにくさやストレスの原因が改善され、結果的に働きやすい職場づくりにつながります。
【企業側】
◎離職・休職の予防になる
メンタル不調が悪化する前に対応できれば、突然の休職や退職を防げます。人材の流出はコストも大きく、早めの対策が効果的です。
◎職場の課題を“見える化”できる
ストレスチェックの集団分析を使えば、「どの部署がストレスを抱えているのか」など数値として把握できます。
◎健康経営のアピールになる
ストレスチェックを導入していることは、従業員や取引先への信頼にもつながります。とくに健康経営優良法人認定を目指す企業には大きな加点要素に。
◎労務トラブルの予防になる
職場のストレス対応を怠ったことで問題が起きた場合、企業が責任を問われるケースも。ストレスチェックの実施は、「適切な対応をしている」証拠にもなります。
◎従業員のやる気と生産性が上がる
安心して働ける環境は、自然とやる気や集中力にもつながり、結果的に会社の成果にもプラスになります。


ストレスチェックを実施し、早めに気づくことができ、労働者側にも企業側にもたくさんのメリットがあります。
ここからは、ストレスチェック導入の企業が増えている理由の一つの「健康経営優良法人認定制度」についても見ていきましょう。
2.健康経営優良法人とストレスチェックの関係
「健康経営優良法人認定制度」は経済産業省が健康経営の取り組みをする企業を応援するために、2016年に作られた評価制度です。
その認定要件の中の1つに、『③50人未満の事業場におけるストレスチェックの実施』があります。

健康経営優良法人の認定要件も一緒に見ていきましょう!
(1)ストレスチェックは必須項目?
中小規模法人部門のストレスチェックは2025年現在、必須項目ではありません。
ですが、健康経営優良法人の認定、特に「ブライト500」や「ネクストブライト1000」を目指すなら、導入しておいた方が圧倒的に有利です。
なぜなら、ストレスチェックは認定要件の評価項目①〜③のうち2項目以上達成する、の中に含まれているからです。
【評価項目】
①定期健診受診率(実質100%)
②受診勧奨の取り組み
③50人未満の事業場におけるストレスチェックの実施

つまり、①〜③の項目のうち2つ以上はやらなければいけないということ。
また、「ブライト500」や「ネクストブライト1000」に入りたい場合は上記①〜③含めた15項目のうち13項目以上達成しなければならないので、ストレスチェックは導入しておいた方がいいでしょう。
 健康経営のメリットは何?企業にとって得しかない5つの理由
健康経営のメリットは何?企業にとって得しかない5つの理由 (2)【常時50人以上の労働者を使用する事業場に義務付けられました】の”常時”とは?
(3)ストレスチェックのチェック項目
経済産業省が認定している「健康経営優良法人認定制度」には、申請する時に以下のチェック項目があります。
Q.労働安全衛生法に定められたストレスチェック制度に従ってストレスチェックを実施していますか?
1.労働安全衛生法に定められたストレスチェックについて、労働者が50人未満の事業場を含む全ての事業場で、適切な者(医師、保健師または厚生労働大臣が定める研修を修了した歯科医師、看護師、精神保健福祉士もしくは公認心理師)がストレスチェック実施者として実施している
2.上記以外の方法で実施している、または全ての事業場では実施していない⇒評価項目不適合

労働安全衛生法に定められたストレスチェックを実施しているかを問われていますね。
他にもこんなチェック項目があります。
Q.自社従業員の健康課題を踏まえ、健康経営の具体的な推進計画等を定めていますか?
1.具体的な推進計画を策定し、数値目標、実施主体、達成期限を定めて推進している
2.特に定めていない(定めていない項目がある) ⇒健康経営優良法人不認定
⬇️
Q上記で1と答えた場合、どのように従業員の健康課題を把握していますか。(いくつでも)
1.健康診断結果を集団ごとに集計・分析をして把握している
2.ストレスチェック結果を集団ごとに集計・分析をして把握している
3.勤怠管理システム等から勤怠データ、有給取得状況等を集計・分析をして把握している
4.産業医、保健師、地域産業保健センターの担当者等の産業スタッフとの対話を通して把握している
5.保険者との対話を通して把握している(協会けんぽが実施するヘルスケア通信簿等を含む)
6.健康経営アドバイザーや外部コンサルとの対話を通して把握している
7.独自に健康課題に関する従業員アンケートを実施して把握している
8.従業員との個別面談やミーティングを通して健康課題を把握している
9.従業員本人に健康課題や目標を記載してもらっている

ここでもストレスチェックを実施していれば項目を満たすことができます。
ストレスチェック結果を集団ごとに集計して分析し、担当者や事業主がきちんと把握するようにしましょう。
3.企業の成功事例

実際にストレスチェックを導入している企業の成功事例を見てみましょう。
(1)株式会社コー・ワークス(宮城県仙台市)
メンタルヘルス推進担当者2名、健康経営の取組みを進める担当者2名と、外部の公認心理師の方と顧問契約して様々なサポートをしてもらいながら、従業員が笑顔で過ごせるようにメンタルヘルス対策の取組みを進めている株式会社コー・ワークスさん。
外部の公認心理師に実施者をお願いしてストレスチェックを実施しています
「当社の従業員数は50人未満ですので、ストレスチェックの実施義務はありませんが、2019年からストレスチェックの実施を始めました。ストレスチェック実施者は、当初より外部の公認心理師の方にお願いしています。」
(中略)
ストレスチェック後は従業員面談も実施し、職場環境改善につなげています
「ストレスチェックは、現在、年2回実施しています。また、年1回は、ストレスチェック実施後に私(岡村さん)が全員と面談を実施し、会社に対して不安に感じていることなどについて話を聞いています。高ストレス者の方には、私(岡村さん)や外部の公認心理師が補足的に面談を行い、その面談結果を参考にした上で、医師による面接指導の対象者を判断しています。」
(後略)

・ストレスチェックを年2回実施
・年1回は担当者が全員と面談を実施している
とても手厚くストレスチェック、メンタルヘルス対策をしていて、従業員の方々も安心して働くことができますね。
(2)苫小牧飼料株式会社(北海道苫小牧市)
“健康経営優良法人2024(中小規模法人部門)ブライト500”の認定を受けた苫小牧飼料株式会社さん
メンタルヘルス対策として学んだ話の聴き方が管理職の部下とのコミュニケーションに役立っています
「これまで、精神疾患を理由に休んだり辞めたりする社員はいなかったため、健康経営に取り組み始めるまではメンタルヘルス対策を積極的には行っていませんでした。メンタルヘルス対策として最初に取り組んだのは、苫小牧市の“ゲートキーパー養成講座”の受講です。自殺予防対策の講座でしたが、話の聴き方や日頃からの社員へのケアの方法について学ぶことができました。講座で教わったことを私が社内で実践し、社員が話しやすい雰囲気づくりを意識したり、心の中のモヤモヤなど溜まっているものを出してもらうようにしたりしています。話を聴く中では、まず最初に褒めるということを意識しています。そして、話を聴く中で対応が必要なことがあればすぐ対処しています。最近は、このような話し方を他の管理職も真似しはじめており、部下とのコミュニケーションに役立っているようです。」
(中略)
「当社の健康経営の指標として“健康経営KPI”を定めています。その項目の1つが“ストレスチェック受検率”です。2022年度は91.6%でしたが、2023年度は100%と全員が受検しました。健康に働き続ける上で、自分のストレス状態について知ることが重要だという会社のメッセージが、着実に社員へ伝わっているのではないかと思います。」

講座で学んだ話の聴き方や日頃の社員へのケア方法が社内に浸透し、2023年度にはストレスチェック受検率が100%になり、会社の健康経営への思いが着実に社員に伝わっていますね。
4.ストレスチェックの導入
ストレスチェック導入の際にはしっかりとした体制を整える準備が必要です。ステップ①〜⑨にのように準備・実施をしましょう。
ステップ①
目的をはっきりする
「社員の健康を守りたい」「健康経営の認定を取りたい」など、導入する理由を最初に整理し決めておく。
その内容を従業員にも周知する。
ステップ②
実施の体制を決める
ストレスチェックは、医師・保健師など専門の資格を持つ人が「実施者」として必要です。
社内にいない場合は、外部に委託する。
ストレスチェック担当者を決める。
ステップ③
質問内容を決める、もしくは、外部の委託業者を決める
⬇️質問内容を決める際はこちらを参考に。
職業性ストレス簡易調査票(57項目)(出典:厚生労働省より)
⬇️委託業者を決め流歳はこちらを参考に。
外部機関にストレスチェック及び面接指導の実施を委託する場合のチェックリスト例(出典:厚生労働省より)
ステップ④
実施方法を選ぶ
紙で実施、もしくはオンラインで実施。
従業員それぞれにに合わせて選択制にするのもあり。
ステップ⑤
回収・評価をする
実施者もしくは担当者が、回答内容が見えないように封筒などに入れるなどして回収し、高ストレス者の選定をする。
⚠️第三者や人事権を持つ職員が、記入・入力の終わった調査票を閲覧してはいけません。
ステップ⑥
本人に結果を通知
結果は実施者から本人に通知する。
高ストレス者には通知をする際に、面接指導の対象者であることを伝え、申し出るよう勧奨する。
ステップ⑦
医師による面接指導の実施
産業医資格を有する医師が望ましい。
従業員の状況によっては専門医療機関への受診勧奨が必要な場合もあるので、メンタルヘルスに関する知識を持っているのか、確認するといい。
ステップ⑧
就業上の措置を実施
対象者本人の同意のもと、事業者に医師との面接結果などを提示し、事業者は就業制限や要休業など、プライバシーに配慮しつつ従業員に合わせた措置の実施をする。
例えば、就業制限(労働時間の短縮・就業場所の変更)や、要休業(休暇または休業により一定期間期間勤務させない措置)などを講じる。
ステップ⑨
集計・分析
対象者が10人以下の場合、個人が特定される可能性があるため、対象者全員の同意がないと集計・分析結果は事業者に提出できません。同意が得られない場合は特定されない方法で事業者に提示します。
【個人が特定されない集計結果の例】
・ストレスチェックの総合点の平均値
・仕事のストレス判定図の提示
また、分析結果は経年変化を見るために5年間保存しておくことが望ましい。

ストレスチェックは単なる“アンケート”ではなく、従業員と会社、どちらにとっても早めに気づき予防できる仕組み(システム)です。しっかりと段階を踏んで実施し、従業にとっても事業者にとっても居心地の良い職場環境にしていきましょう。
5.まとめ
◎ストレスチェック制度
▶︎50人未満の事業場には義務はないが、「健康経営優良法人認定」を目指すなら実施した方がいい
▶︎従業員の心の状態を“見える化”する簡易検査
▶︎認定の評価項目「①健診率」「②受診勧奨」「③ストレスチェック」のうち2つ以上を満たす必要がある
▶︎労働者には安心して相談できる環境ができ、メンタル不調の早期発見につながる
▶︎企業側には離職防止・職場改善・外部評価の向上など多くのメリットがある
◎導入は以下の9ステップ
①目的を明確にする
②実施体制を整える(社内 or 外部委託)
③質問内容 or 委託業者を選定
④実施方法を選ぶ(紙・オンライン)
⑤回収と評価(プライバシー厳守)
⑥本人に結果通知、高ストレス者へ勧奨
⑦医師による面接指導の実施(本人同意が必要)
⑧必要に応じて就業措置(本人同意の上)
⑨集計・分析(個人が特定されない形で)
◎高ストレス者の情報は本人の同意がなければ会社に提供不可
 【健康経営優良法人】メンタルヘルス不調者への対応に関する取り組み
【健康経営優良法人】メンタルヘルス不調者への対応に関する取り組み  【2026 健康経営優良法人】運動機会の増進に向けた取り組み
【2026 健康経営優良法人】運動機会の増進に向けた取り組み  【2026 健康経営優良法人】食生活の改善に向けた取り組み
【2026 健康経営優良法人】食生活の改善に向けた取り組み 
