このブログは約5分で読めます。
夕食後、ソファに座った瞬間、「お腹いっぱいで動けない…」と感じたことはありませんか?
実は、食べ過ぎを控え、少し手を止めるだけで、体と健康を守ることができます。その知恵が、日本の昔ながらの「腹八分目」です。

こんにちは、Sailing Dayの羊一です。
このブログでは「腹八分目」について詳しく解説します。
1. 腹八分目とは?
「腹八分目」という言葉は、日本の健康や食生活の考え方でよく使われます。
「お腹いっぱい!」と感じるのが、腹十分目。
「もう少し食べたいな」と感じるくらいが、腹八分目とされています。
つまり、満腹になる前に食事を終えることを指します。
(1)腹八分目を取り入れる4つのメリット
①消化器官に優しく胃腸の負担を軽減
満腹になるまで食べると、胃や腸には大きな負担がかかります。消化に多くの血液が必要となり、胃もたれや消化不良、さらには胃酸の逆流や膨満感の原因になることも。
腹八分目で食事を終えると、胃腸にゆとりができ、消化がスムーズになります。また、胃腸への負担が軽減されると自律神経のバランスも安定しやすく、体全体の調子が整いやすくなるのも大きなポイントです。
②太りづらく生活習慣病のリスクを軽減
食べすぎは、肥満の最大の原因です。肥満は高血圧、糖尿病、脂質異常症などの生活習慣病のリスクを高め、心血管疾患や脳卒中の発症にも関わります。
腹八分目を意識することで、自然と1回あたりのカロリー摂取量を抑えられ、無理な食事制限をせずに健康的な体型を維持できます。さらに、腸内環境も整いやすくなります。
③食後の眠気や集中力低下を防ぐ
昼食後や夕食後に眠くなるのは、食べすぎによって血液が胃腸に集中し、脳への血流が減るためです。血糖値の急上昇・急降下も眠気や集中力低下に拍車をかけます。
腹八分目にすることで、消化がスムーズになり、血糖値の急変動も抑えられます。
その結果、午後の仕事や勉強のパフォーマンスが落ちにくくなり、集中力や判断力を維持しやすくなります。

④精神面も安定ストレス軽減に
食べすぎは胃腸だけでなく、気分や精神状態にも影響します。過食による消化不良はイライラや不安の原因となることも。
腹八分目を意識することで、自律神経のバランスが整い、精神的にも落ち着きやすくなります。
さらに、よく噛んでゆっくり食べることで、脳内の「幸せホルモン」と呼ばれるセロトニンが増加。リラックス効果が高まり、食後のストレスや罪悪感からも解放されます。
(2)企業でも注目!腹八分目は健康経営にも効果的!

最近では、社員の健康を守る「健康経営」の取り組みとして、腹八分目を意識した食生活改善が注目されています。
三重スバル自動車株式会社では、腹八分目運動として毎月「8」のつく日を「腹八分目運動」と定め「腹八分目の食事」と「よく噛んで食べる」を意識する日としています。
まずは、月に1回から進めてみるのもおすすめです!
(参考:2022年度 三重スバル健康経営の取り組みについて)
▼A4で印刷できます。休憩室や食堂に貼って、腹八分目を目指しましょう。

健康経営として取り組む際のポイント
① 社員の意識をまずは把握する
「昼食で満腹まで食べることが多いか」「夜食や間食が多いか」「腹八分目を意識したことがあるか」など社内アンケートで食事習慣を確認してみましょう。
②成果を見える化する
「昼食後の眠気が減ったか」「午後の集中力はどうか」「満腹感の満足度は?」などアンケートで満腹感や体調、集中力の変化を聞いてみましょう。結果を社内報や掲示板でシェアすると、他の社員の参加意欲も高まります。
上記、2点はすぐにでも取り組めますのでチャレンジしてみてください。

腹八分目運動は、社員一人ひとりの健康を守りつつ、企業全体の生産性アップにもつながる、まさに「体にも会社にもやさしい習慣」です。
▼健康経営優良法人の取得項目にも食生活の改善があります!
 【2026 健康経営優良法人】食生活の改善に向けた取り組み
【2026 健康経営優良法人】食生活の改善に向けた取り組み 2. 腹八分目の3つのポイント
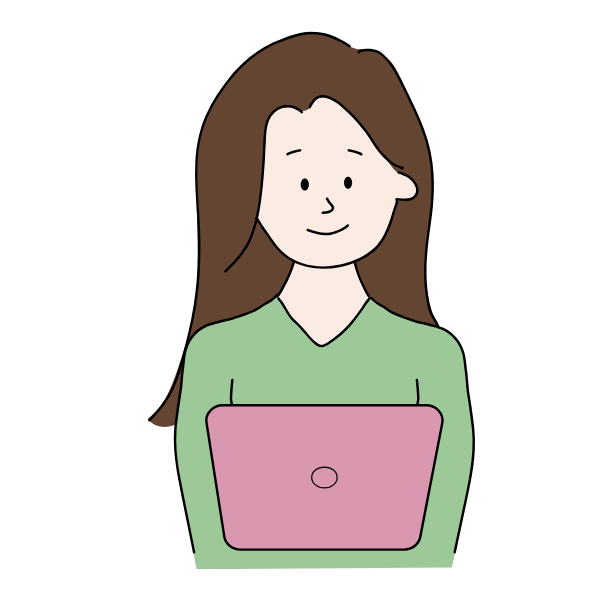
「腹八分目」ってよく聞くけど満腹にならず、つい間食をしてしまいそうだなあ。

実は、ポイントを押さえれば、しっかり満腹になって「腹八分目」で満足できるようになるんですよ。
①食べるスピードをゆっくり
ポイントはよく噛む、ゆっくり食べること!
脳が「満腹」と感じるまで時間がかかるため、早食いだと食べすぎてしまいます。
箸を置く→水を一口→また食べるを繰り返して、食事時間自体を長くするのもおすすめです!
②お皿に盛る量を少なめに
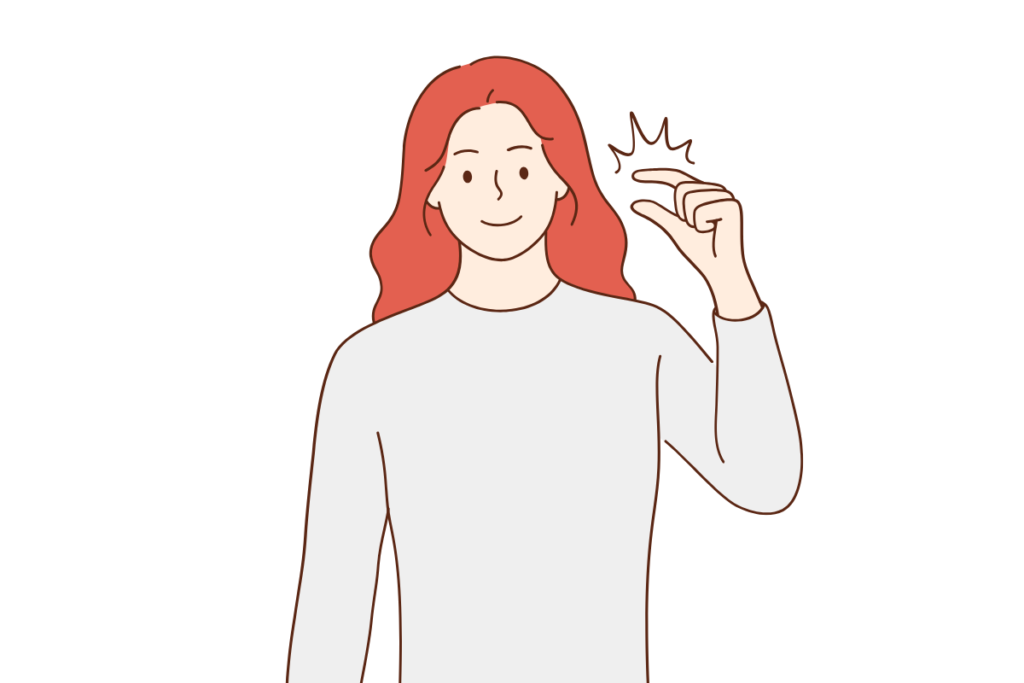
ポイントは食事を最初から少なめに盛ること!
目で見て量を調整できるので、まずは何か一品決めて、そのものを普段の8割程度にしてみましょう。
昼食をコンビニで買っている方は、おにぎりの個数を減らしてみることからチャレンジ。
外食している方は、注文時にご飯の量を減らしてみましょう。
③食べる順番を工夫
ポイントは野菜や汁物から食べる!
これは夕食時がやりやすいでしょうか?
水分・食物繊維でお腹が膨らみやすく、自然に量を減らせます。サラダ→汁物→主菜→ごはんの順番で食べてみましょう。
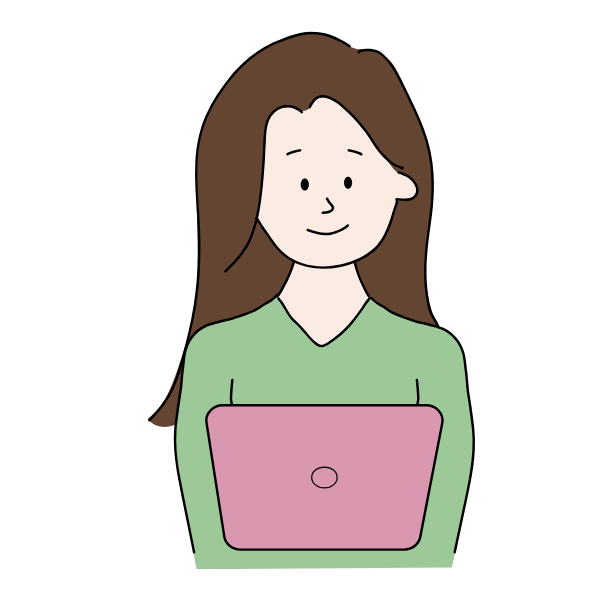
なるほど!この工夫をすると満腹感得られそうですね!
(1)腹八分目実践時の注意点
腹八分目は健康に良い習慣ですが、やり方を間違えると逆効果になったり、体調を崩すこともあります。5つの注意点をまとめました。
① 栄養バランスを崩さない
腹八分目にするあまり、食べる量だけを減らして栄養を削るのはNGです。
野菜やたんぱく質、良質な脂質、炭水化物をバランスよく摂ることが大切です。特に、たんぱく質や野菜不足になると筋肉量低下や便秘の原因になることも‥。
量は控えめでも、質の高い食材をしっかり摂ることを意識しましょう。
② 空腹を我慢しすぎない
腹八分目を意識するあまり、極端に空腹を我慢すると、次のような問題が起こります。
◎食べすぎにつながる反動(ドカ食い)
◎血糖値が急に下がって頭痛やめまいが起こる
◎精神的ストレスになり、続けにくくなる
腹八分目は「満腹になる一歩手前」を目安に。お腹が7〜8割満たされれば十分です。
③ 食事内容やタイミングを考える
腹八分目でも、高カロリー・高糖質・高脂質の食事ばかりだと意味がありません。
揚げ物やスナック菓子ばかりだと肥満や生活習慣病リスクは下がりませんし、夜遅くに食べすぎると消化が悪く、睡眠の質にも影響与えてしまいます。
腹八分目を意識するなら、野菜中心・消化の良い食材を取り入れることが望ましいです。
④ 無理に減らさない
腹八分目はあくまで習慣として少しずつ取り入れるのがコツです。
最初から毎回8割に抑えようとするとストレスになってしまうので「今日はちょっと多めでもいい」と柔軟に考えることが長続きできる秘訣です!
「1日1食だけ腹八分目を意識してみる」など段階的に取り入れると成功しやすいです。
⑤ 個人差を意識する
体格や運動量、年齢によって、腹八分目の目安も変わります。
例えば、運動量が多い人はやや多めでもOKですし、消化機能が弱い人や高齢者は、ゆっくり食べることがより大切です。
自分の体調や生活リズムに合わせて調整しましょう。

腹八分目は「量を減らすこと」だけでなく、「栄養・満腹感・生活リズム・体調」を意識して取り入れることが大切です。
3. まとめ
◎ 腹八分目とは
▶︎ 満腹になる前に食事を終えること。「お腹7~8割でOK」
◎ メリット
① 胃腸にやさしく消化スムーズ
② 太りにくく生活習慣病リスク減
③ 食後の眠気・集中力低下を防ぐ
④ 精神安定・ストレス軽減
◎ 実践ポイント
① 食べるスピードをゆっくり(よく噛む)
② お皿の量は少なめ(最初から8割程度)
③ 食べる順番を工夫(野菜→汁物→主菜→ごはん)
◎ 注意点
▶︎ 栄養バランスは崩さない
▶︎ 空腹を我慢しすぎない
▶︎ 食事内容・タイミングを意識
▶︎ 無理せず少しずつ習慣化
▶︎ 個人差に合わせて調整
◎ 企業での活用例
▶︎ 「8」のつく日を腹八分目デーにして、社員の健康と集中力UP
 【健康経営】忙しくてもできる!1日1つの食生活改善で疲れにくい体に
【健康経営】忙しくてもできる!1日1つの食生活改善で疲れにくい体に  【健康経営×食生活改善】社員の健康を支えるおすすめ食材と実践アイデア
【健康経営×食生活改善】社員の健康を支えるおすすめ食材と実践アイデア  【健康経営】食生活の改善で職場が変わる!今日からできる実践アイデア
【健康経営】食生活の改善で職場が変わる!今日からできる実践アイデア 
